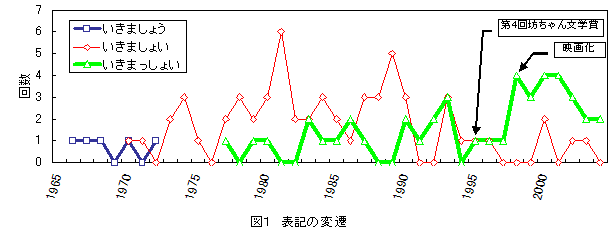|
�@ �@ �w������Ă����܂��傢�x�ɂ��� �@ �@ �@ �����g�p�ၫ�� �@ �ʏ�o�[�W�����imp3�@0.2MB�j ����Y�o�[�W�����iwmv�@4MB�j ���O�r�[�������O�o�[�W�����iwmv�@1MB�j�@ �@ �@ �@ ���k�����OB�̏،������ƂɌ��t�̃��[�c�ׂĂ݂܂��� �@ �@ |
|
�@ |
|
���u������Ă����܂��傢�v�̗R���ƕϑJ�@2024.10���@�@����pPDF�@ �iWEB�ł�PDF�ł͎�قȂ�܂��BPDF���ŐV�o�[�W�����ł��j �@ �P�D�͂��߂� �@ �@����17(2005)�N7�`9���C�t�WTV�n��Ńh���}�u������Ă����܂����傢�v���������ꂽ�B�����܂ł��Ȃ��~���ǎq����̏����u������Ă����܂����傢�v�m��4��V������w�ܑ��܁F����7�N�n���h���}�����ꂽ���̂ł���B����10�N�ɂ͓c����ގ剉�ʼnf�扻����Ă������C�����o�āC�ߘa6�N�ɂ͌���A�j�������J�����Ƃ����B
�@ �@���̂悤�Ȕw�i����C�u������Ă����܂��傢�v�Ƃ������t�̗R���E�ϑJ�ɂ��Ē��ׂĂ݂��B �ʐ^1�@�L�O��i���i�j
�@�@�@�@�@�@ �ʐ^2�@�L�O��i�ߌi�j �ʐ^3�@�����r�O ���@�i���� ��24�����j �Q�D�R���E�ϑJ �Q�D�P�@�R�� �@ �@�܂��C���k��u���v(���a39�N�x�n��)�ׂ��Ƃ���C����19��(���a57�N�x)�ɉ��{�F�������̊�e���������B�܂��́C���̑S�����ȉ��ɓ]�ڂ����Ă��������B �u�撣���Ă����܃V���C!!�v���������̋L �@�v���U��̎��Ƃ�k�Ƃ̐ڐG�������������҂ɋ����͂��܂��Ă��̊w�Z�ɕ��C���ė����̂����a40�N�̏t�C37�̂Ƃ��ł��B�z�[�����[���S����1�N7�g�B�u�������āC���Ɋw�Ԃ��ƂɂȂ�܂����B���݂��Ƀ��b�L�[�Z�u�����ɂ��悤�B�v�ƁC���A�������Ƃ𖢂��ɖY��܂���B�����̏��R������1�w��50���C1�w�N12�N���X�őS�Z���k1,800���̃}�����X�Z�ł����B���x�ׂ�8�g�̃N���X�S�C�������r�O�搶�ł����B���̍����搶�Ƃ̏o�������C�撣���Ă����܃V���C!!�ݏo�����傫�ȗv���ł��B���̑O�C�͌�����ψ���ی��̈�w���厖�B���x�O�N�̏H�̌�����ō����搶���������\�����܂����B�v�|�͑̈���Ƃ̖����Ԃ�10���Ԃ̑��^�������{���C�̗́C�C�͂�{���ƌ������Ƃł����B�f���炵���v�悾�Ə^�̌��t�𑗂������Ƃ��L�����Ă��܂����C����Ȃ������̒��ŗ��t�����搶��2�l�Ńz�[�����[�����C�ی��̈�����̔N��1�N����S�����邱�ƂɂȂ�܂����B�Ƃ��ɍ����搶��30�ɂȂ�������ł���C���͂���܂�5�N�ԉ^�����Ă��Ȃ���ɁC�N�ߓI�n���f�B�[������C�O�����h�ł̊����ɂ͈ꖕ�̕s���������Ă��܂����B�������C�O�N�܂ő̈�̐搶���Ɉ̂����Ȃ��Ƃ������Ă����̂ł�����C�]�肢�������Ȃ��Ƃ͋�����܂���B�O�N�̑��^���̌v������{�Ɉڂ��܂����B���s���Ƃł��̂�2�l�ŒS���������Ƃ͉����������J�u�ł��B�W�c�̐擪�ɗ����Ė�����10���Ԃ̑��^���͂��̎��̎��ɂƂ��Ă͑�ςȂ��Ƃł����B���C�����搶�ɕ������̂ł͎����̒S�����Ă��鐶�k�ɐ\����Ȃ��C����H������撣�葱���܂����B�g�̂������܂ł́C���Ă��܂��ĉƂɋA���Ă���������Ȃ������ƁC�����ɉƓ��Ɍ����܂��B �@ �@�W�c���̐^���́C���������Ȃ���50�l�̑�����1�ɂȂ��ăO���E���h�ɂ����܂��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B6�C7���o�ƁC���v�͂̂���҂ƂȂ��҂Ƃ̍����o�đ��������ꂪ���ɂȂ�܂��B�N�������Ƃ��Ȃ��C�撣�낤!!�Ƃ��������o�đ����͂܂����Ƃ�1�ɋA��܂��B���́u�撣�낤�v�́C���ɂƂ��Ă��~���̐��ł����B�����搶�ɕ����Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�C���k�ɕ����Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�������ƁB���ɔG��C������ɂ܂݂�C����H������C�Ђ����瑖�葱���钆�Ő��k�B�̗l�X�Ȑ����o�Ă��܂����B�撣��C�撣�낤�C�撣���čs���������������āC�u�撣���Ă����܃V���C!!�v�͂��̐��k�B��3�N���̎��́C�^����Ő��܂ꂽ�ƋL�����Ă��܂��B���̔N�͍��Z���̂ɍ����搶�̃��O�r�[�C���̃o�X�P�b�g�{�[�����܂݁C5��ڂ𐧔e���܂����B�܂��C�����升�i�҂̋L�^���ЂɍX�V���܂����B�u�撣���Ă����܃V���C!!�v�́C����������ڎw���āC�������葱�����C���̎��̐��k�B�̍������t�ł����B �m���{�F���C����19�������p�n �@ �@���{�搶�̊�e�ɂ��C�W�c���̒����玩�R�����I�ɐ��܂ꂽ���̂Ƃ̂��Ƃ��B�����āC�����s���Ŏg����悤�ɂȂ����̂́C���a42�N�̉^����Ƃ������ƂɂȂ�i�������͌�q�̒ʂ菺�a41�N�j�B �@���Ȃ݂ɑ̈���ƒ��̏W�c���ɂ��č����搶���C�w����(���a36�N��)��80�����Ƃł������̂ő̈���Ƃ�15���̏W�c���v���C10���Ԃ̓����̑�����ѕ⋭�^���C50���̉^���̈�(�N�Ԍv��ɂ��ƂÂ����㋣�Z�C���Z�����)5���Ԃ̐����^���������Ԃ̔z���ł������B�x�Ɛ���3��(���a41�N�x)�ɋL�q���Ă���B�̈�̎��Ǝ��Ԃ���������������̂ł���C10�`15���Ԃ̎��v����������邱�Ƃ��ł����ł��낤�B �@�b��߂��ƁC������u�����v��34��(2004)�ɂ́C�����������������L�̂悤�ɋL���Ă���B �w���̌��t�́C���N�x�̓�����ߋE�x������ɎQ�������ۂɁC���a43�N3�����Ƃ̏�c������u2�N���̎�(���a41�N)�C�̈�S���̍����r�O�搶(���a36�`49�N�{�Z�ݐE)���珀���^���̂������̍ۂ̂��������l����ƌ���ꂽ�B���낢���Ă��������炱�̌��t�ɗ��������C�������������Ƃ��Ĕ������B�₪�Ă��̌��t�́C�������̃N���X�ł��������Ƃ��Ĕ�������悤�ɂȂ����B�Ȃ��C�ŏ��ɑS�Z���k�̑O�ł��̌��t��吺�Ŕ������̂́C�����̖싅���叫�̑唺���v�N�ł������B�v�Ƃ������Ƃ����������܂����B�x �@ �@����ɖ싅�����I�����i�b�q���j�ɏo�ꂵ���ہC����27(2015)�N3��29���̃X�|�[�c���Ɉȉ��̋L�����������B �@ �@�ȏォ��C���t�����܂ꂽ�̂͏��a41�N�ł���C�̈���ƒ��̏W�c���ɂ����āC�����搶�̎w���ɂ�萶�k�����ꂱ��l���C�u������Ă����܂��傤�v�ɗ����������Ƃ������Ƃ̂悤���B�������C�����́u���傢�v�ł͂Ȃ��C�u���傤�v�������悤���B �Q�D�Q�@�ϑJ �@ �@�O�q�̎����W�������ł��m�F���ׂ��C�u���v�ɓo�ꂷ��u������Ă����܂��傢�v�̕\�L���s�b�N�A�b�v���Ă݂��B������\1�ɂ܂Ƃ߂�B����݂Ԃ��ɒ���������ł͂Ȃ��̂ŁC�R�ꂪ���邱�Ƃ͂��e�͊肢�����B �@ �@�\1�Œ��ڂ��ׂ����Ƃ́C���a41�`45�N�x�ɂ����āC�u�����܂��傤�v�Ȃ����u�����܂���[�v�Ƃ����\�L���ڗ����Ƃł���B�ǂ���珉���̍��́C�u�����܂��傤�v�Ƌ���ł����悤�ł���B�����ŁC���a43�N���Ƃ�OB�ɕ����Ă݂��B���̕��ɂ��ƁC�w�����搶�����Ƃ̒��Łu�������C�ŁC�݂�Ȃ��ە�����悤�Ȋ|�����͂Ȃ����v�ƌ����o�����B�����́u���������v���Ƃ��u�撣��撣��v�C�uLet�fs Go�v�ȂǂƂ��낢��ƌ����Ă����̂��C�N����ƂȂ��u�撣���Ă������v�������Ƃ������ƂɂȂ�C���ꂪ�������u������Ă����܂��傤�v�ɕω������B�x�Ƃ������Ƃł���B��͂菉���́u������Ă����܂��傤�v�Ƌ���Ă����̂��B �@ ����3��(���a41�N�x)�̉^����ɂ́w�u�K���o�b�e�C�L�}�V���E�B�v�唺�N�̑吺�ɂЂƂ��퍂�������B�x�Ƃ̋L�ڂ�����B���̋L�q���������Ƃ���ƁC���{�搶�̊�e�Ɩ�������B���a41�N�̉^����ł��łɋ���Ă������ƂƂȂ�B�O�f�����X�|�[�c���̋L���ɂ�41�N�Ƃ���̂ŁC41�N���������̂ł��낤�B���OB�ɕ������Ƃ���C�w���̌��t���蒅�����̂́C���a42�N�̉^����ȍ~�ƋL�����Ă���B���̔N����̗p���ꂽ�_�̑��̖`���ɁC�唺����̏ォ��u������Ă����܂��傤�v�Ƃ����|�����������C���̌㉉�Z���J�n���ꂽ�̂��B�x�Ƃ̂��ƁB����ɂ́C�w���̖_�̑�����ϗE�s�ōD�]�������Ƃ���C�����搶���u���܂���悩�������v�ƁC�܂��݂Ȃ���J�߂Ă����������L��������B�x�Ƃ����B���{����������42�N�̈�ۂ����������̂ł��낤�B���a41�N�x�̉^����ɂ����đ唺����ɂ�苩�ꂽ���C�w�Z�s���ł̔����Ƃ��čL���F�m����C�F�̋L���ɋ����c�����̂͏��a42�N�x�̉^����̖_�̑��Ƃ������ƂƉ��߂���B�֑��Ȃ��炱�́w�唺�N�x�C���a41�N������2�N���B3�N�����͖싅���叫�Ő��O���[�v���B����ɍ�3�N�̎��ɂ́C�t�B�M���A�X�P�[�g�ō��̏o��̌o���������|�ȕ����B �@ �@�u�����܂��傢�v�Ƃ����L�q�́C���a45�N�x�ɏ��߂ēo�ꂷ��B�����C���ۂ̔����́C�u�����܂��傤�v�Ɓu�����܂��傢�v�̒��Ԃ̂悤�Ȋ����������̂�������Ȃ��B�O�o��OB�́C�w���`���������āu���傢�C���傢�v�Ƃ������Ƃ����X�������B�x�ƌ����B�u���傤�v�u���傢�v�������g���Ă����̂ł��낤�B���ꂪ���a45�N���܂łɂ͏��X�Ɂu���傢�v�Ɏ��ʂ��ꂽ���̂ƍl����B�w�u���傤�v�ƃm�[�}���ɔ��������̂ł͂܂�Ȃ��B������ƂЂ˂��āu���傢�v�Ƃ����������ʔ�������Ȃ����B�x�Ƃ������ƂŁu���傢�v���D���ɂȂ����̂�������Ȃ��B�������Ȃ炳������Ȃ�ł���B���̌�́C�قڂ��́u�����܂��傢�v���g���Ă����Ƃ���C���a52�N�x�Ɂu�����܂����傢�v�Ƃ����\�L�����o�ꂷ��B�~���ǎq�����Z1�N���̎��̂��Ƃł���C�����[���B �@ �@���ɁC�\�L���u�����܂��傤�v�u�����܂��傢�v�u�����܂����傢�v�u���̑��v��4�ɕ��ނ��Đ����J�E���g���Ă݂�(�\2)�B������O���t�ɂ����̂��}1�ł���B1960�N��́u�����܂��傤�v�C1970�`1980�N��́u�����܂��傢�v�C1995�N�ȍ~�u�����܂����傢�v���D���ł��邱�Ƃ��킩��B����1998�N�̉f�扻(�剉�F�c�����)�ȍ~�́u�����܂����傢�v�̗D���������ł���B2005�N�ɂ̓e���r�h���}�����ꂽ���Ƃ�����C��������̌X���͑������̂Ǝv����B �@
�@ �@�\1������ƁC�Z���搶�⋳���搶���u������Ă����܂��傢�v��p���Ċ�e���Ă���B5�������邱�Ƃ��ł������C�S�āu�����܂��傢�v�Ƃ����\�L��p���Ă���B���̂����肪�C�L�O��̕\�L�Ɂu���v������Ȃ��������R�ł��낤�B�w�Z���u�����܂��傢�v���̗p���Ă���̂́C���a53�N�ɑn��100���N�L�O���s���Ƃ��āC�u������Ă����܂��傢�@���R�����̎l�G�v�Ƃ������Ђ������̍Z�������o�搶�ɂ��ďC�Ŕ������ꂽ���Ƃ��傫�ȗ��R�ł͂Ȃ����ƕM�҂͍l����B �@ �@�ʔ����\�L�Ƃ��ẮC�w�u�Ђ��������������@���\�\���Ă���������储�����v�Ƃ�������̂͂킽�������ł͂Ȃ��͂����B�x�Ə����Ă��鐶�k�������B�m���ɁC���ѕ��C�������ɂ���ėl�X�ɕ�������ł��낤�B�u�����܂��傢�v�����ł���C�u�����܂����傢�v�����Ȃ̂��B���������������̕\�L�̖������C�ЂƂ̌��t��������č��Z���B�Ɏg��ꑱ���Ă��邱�Ƃ��f���炵���B �@ �@�Ȃ��C���ɏ��o�ꂷ��L�q�́C�w�u�K���o�b�e�C�L�}�V���E�B�v�唺�N�̑吺�ɂЂƂ��퍂�������B�x�Ƃ������̂ł���C�w�ЂƂ��퍂�������x�Ƃ���̂ŁC�u�V���E�v�Ƃ������̎肪�Ԃ������ǂ����͋^��ł���B�u���傢�v�̂Ƃ������̎肪�����甭�������悤�ɂȂ����̂��ɂ��Ă͒肩�ł͂Ȃ����C���Ȃ��Ƃ����a46�N�x�̐��ɂ͊m�F�ł���i�\1�j�B
�Q�D�R�@�܂Ƃ� �@ �@�ȏ�̎����W������ƁC�w������Ă����܂��傢�x�̗R���E�ϑJ���ȉ��̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł���B �@ �@�@�@���a41�N(1966�N)�ɍ����搶�E���{�搶�w���̏W�c���̒���, �����搶�������|�������l����悤�ɐ��k�Ɏw�����C��X�l�������ʁC�w������Ă����܂��傤�x�ɗ����������B�����ē���2�N���̏�c�����Ƃŏ��߂Ĕ������B �@�@�A���̌��t�́C�����ق��̃N���X�ɂ��L�܂��Ă������B �@�@�B�����s���Ƃ��ẮC���a41�N(1966�N)�̉^����ő唺����ɂ��C�w������Ă����܂��傤�x�Ƌ��ꂽ�B �@�@�C�L���F�m����蒅�����̂́C���a42�N(1967�N)�̉^����ł���B�_�̑����Z�J�n�O�ɐ��O���[�v���̑唺���d�ォ�狩���̂ł���B �@�@�D�����́w�����܂��傤�x�Ɣ������Ă������C������炯���甭�������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����w�����܂��傢�x���g���͂��߁C���a45�N(1970�N)�ȍ~�́w�����܂��傢�x�Ƌ���邱�Ƃ������Ȃ�B �@�@�E�u���傢�I�v�Ƃ������̎肪�����甭������悤�ɂȂ������͒肩�łȂ����C���Ȃ��Ƃ����a46�N�x(1971�N�x)�ɂ͊m�F�ł���B���̍��܂łɂ͌��݂̌`���o���オ�����悤���B �@�@�F1970�N��C1980�N��͂��́w�����܂��傢�x�������p����ꂽ�B �@�@�G���a52�N(1977�N)�Ɂw�����܂����傢�x�Ƃ����\�L���u���v�ɏ��o�ꂷ��B �@�@�H1990�N�㏉���ɂ́C�w�����܂��傢�x�Ɓw�����܂����傢�x���h�R����悤�ɂȂ����B �@�@�I����7�N(1995�N)�ɕ~���ǎq����̏����w������Ă����܂����傢�x����4��V������w�ܑ�܂���܂���B �@�@�J����10�N(1998�N)�ɂ͏������f�扻����C���̍�����C�w�����܂����傢�x���D���ƂȂ�B �@�@�K����15�N(2003�N)�ɂ́C�L�O��w������Ă����܂��傢�x���ݒu���ꂽ�B������w�Z�Ƃ��ẮC�u�����܂��傢�v�𐳎��ȕ\�L�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B �@�@�L����17�N(2005�N)�ɂ́CTV�h���}�u������Ă����܂����傢�v���������ꂽ�B���̉e��������C����́u�����܂����傢�v�������g���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B �@�@�M�ߘa6�N(2024�N)�ɂ͌���A�j�����B �R�D���O�r�[���Ɓu������Ă����܂��傢�v �@ �@���O�r�[���ē̍����搶�����t�̐��������ɌW����Ă��邱�Ƃ�����C���O�r�[���ɂƂ��Ă����̌��t�ɂ͐[���v�����ꂪ����B �@ �@����9��(���a47�N�x)�̃��O�r�[�����ɂ́C�w���K���݂͂�Ȑ^���ł���B����Ȃǂ͕�����Ȃ��B�������u������Ă����܂��傤�B�v�Ƃ����������̂��Ƃɕ��������͋ꂵ�����K�����ɂ̂肫���Ă���B����ă��O�r�[���Ɂu������Ă����܂��傤�B�v�Ƃ����������͋M�d�ł���B�x�Ƃ���B �@ �@�܂��C����14��(���a52�N�x)�̃��O�r�[���Љ�́w�K�b�e���V���C�I�x�Ƃ������t�ōŌ����߂������Ă���B��15��(���a53�N�x)�̃��O�r�[���Љ�ł́C�w�u�����Ă傢�I�v���̂����������C���́C�`�Ȃ����̏ے��ł���C�����āC�̗͂̌��E����S�g�b�B�ɑς�����C�͂̔��[�ł���B����͒P�Ɂu������Ă������傢�I�v�Ƃ������Z�̂��������Z�k���ꂽ�����̂��̂�������Ȃ����C��X�́C���̌��t�ƂƂ��ɗ��K�ɗ�݁C�����āC���̌��t�Ŏ����̐��_�I���܂Ƃ̊����ɏ����������߂Ă����̂ł���B�x�Ƃ̋L�ڂ�����B �@ ���a40�N��́C���K���Ɂw������Ă����܂��傤(���傢)�x�Ƌ���ł����Ǝv���邪�C���X�ɒZ�k����C���a50�N��ɂ́w�����Ă傢�x�ƂȂ������̂ƍl������B���a50�N��̕����ɂƂ��ẮC���K���ɋC�͂��N�������߂Ɋ|�����������t�ł���B�������������g���Ȃ��Ȃ茻�݂Ɏ����Ă���B����10�N���C�����ē����������݂����C���̍��Z���̋C���ɍ���Ȃ������̂��C�蒅���Ȃ������B �@ �@���K���ł͏����Ă��܂����w������Ă����܂��傢�x�ł��邪�C���̍����炩�C�����O�̂������Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ����B�~�w��g��ŁC�L���v�e���̔����̉��C�C���������Ď����ɗՂނ̂ł���m�ʐ^4,5�n�B�܂��C���ł̏�����C�D���J�b�v���͂�Ŕ��������Ƃ�����B����g�l�����A�u���b�N�D�����̂��Ƃ��m�ʐ^6�n�B�O�҂̃o�[�W�����̓��O�r�[���z�[���y�[�W(https://merfc.chu.jp/)�ɂ�������A�b�v���Ă���̂ň�x�����������������B���X�����Ȃ��H�Ǝv�������Ȃ��ɂ������炸�ł͂��邪�C�t���ĂыN�����Ă����Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���B�Ȃ����a50�N��̎����O�̂������́w�C������I�x�ł������悤�ɋL�����Ă���B������w������Ă����܂��傢�x�Ɏ���đ��������ɂ��ẮC�u���v�ł͂킩��Ȃ������B������蒲���ɂȂ炴������Ȃ����C�܂������ł��Ă��Ȃ��B �@ �@�֑��ł͂��邪�C���̈��w���O�r�[���ł́C�u������Ă����܂���[���I�C���C�o���čs���܂���[���I�v�Ɛ����o���đ����Ă��������ł���B���s�̊������Z�́C�u�C����������I�@���[���C���[���C���[���v�Ƌ���ł����Ƃ��B�ǂ��̃`�[���������悤�Ȋ|�����������Ă����Ƃ������Ƃ��B �@ �ʐ^6�@2003�N6�� �l�����A�u���b�N�D�� �@ �S�D������ �@ �@����C��������ɂ������Đ��k��u���v�͑�ώQ�l�ɂȂ����B��������}���قɍs���Ē��ׂ���(����}���ق̑����ɂ����ł��I�I)�C���k��ɘU���ĊW����y�[�W���s�b�N�A�b�v�����肵���B�u���v�ɂ́C�u���Ȃ�ĉ��l�̐l���ǂނ̂��낤�v�Ȃ�Ă����L�q���U������邪�C���̉��́C�Z�j���L���M�d�Ȏ����ł���B���ɁC����11�N�x�ȍ~�C���R�����V���̔��s���r�₦�Ă��錻��(�V�������p�����)�C���̑��݂͑�ς��肪�����B�����ҏW�ψ��̕��X�Ɋ��Ӑ\���グ��B �@���C���_�C�g���C�����C����4�̃O���[�v�������Ȃ��ꌻ�݂̌`�̉^����ƂȂ����̂����a34�N�̂��ƁB���a41�N�ɓ����̑����C���a42�N�ɖ_�̑����^����̃v���O�����ɑg�ݍ��܂ꂽ�B�w������Ă����܂��傢�x�̌��t�����܂ꂽ�̂����x���̍��̂��Ƃł���B���̌�C�\�L�́u�����܂��傤�v�u�����܂��傢�v�u�����܂����傢�v�ƕς��Ă��Ă�����̂́C�������̍����ɗ����C���ɕς�͂Ȃ��B���オ�ڂ�e����q�̎���ɂȂ��Ă��C�̂ƕς炸���厩���̐��_�̉��C�^������N���u�������w���C���k����̗͂ɂ�萬���������Ă���B�u���ꂪ�������v�Ƃ����ƌ����Ă��܂�����܂łł���B���������̔w�i�ɂ́C�A�ȂƗ���铌�����Ƃ�����ە�����w������Ă����܂��傢�x������B�w������Ă����܂��傢�x�́C�����̓������ɂ͟���p���[�ƈ�̊����COB�ɂ̓m�X�^���W�[�ƕ�Z�̌ւ��^���Ă������ʂȌ��t�Ȃ̂ł���B �@ �@ �y�NjL�z ���▾���̒��ɂ́C�u�V���������߂Ă��̊|�����ɐڂ���͓̂��w���v�Ƃ���L�q������������B�������C���ی����ɂ����Ǝn�Ǝ�(�Ζʎ�)�ł̂��Ƃ��Ǝv���B���w����1�N���݂̂ōs�Ȃ��C�S�Z���k�����낤�͓̂��w���̗����ɍs�Ȃ���n�Ǝ��ł���Ζʎ��ł��邩�炾�B�����u������Ă����܂����傢�v�ł͓��w�������̎n�Ǝ��ł��̊|�����ɐڂ���ݒ�ɂȂ��Ă���B����ɁC�u������Ă����܂��傢�@���R�����̎l�G�v�▾����7�����Z���̊�e�ł͂��̂����肪���m�ɋL����Ă���B�Ζʎ����L���Ӗ��ł͓��w���̈�A�̂��̂ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�܂����w���ƌ���������������C�Ζʎ��Ƃ͉������������s�v�Ȏ�Ԃ��Ȃ��������肵�Ă����ł��낤�B�Ȃ̂Łu���w���v���ԈႢ���Ɩڂ�����𗧂Ă����͂Ȃ����C���n�l�Ԃ̐����䂦���C�����͎����Ƃ��Đ������Ă��������B ����Ɏ֑��Ȃ���C�u������Ă����܂��傢�@���R�����̎l�G�v�ɂ͂���ȋL�q������B�w����������Ă����܂��傢�C�ɂ͂т����肵�����C��������������̂́C�Z�̂̍����ł����B�}�ɂ����납��u���X�o���h�̉����������Ă���ƁC�Z�̂̍������n�܂�܂����B�x�C�w���̍s���̎w�����Ȃ��Ă��C�X���[�Y�Ɏ����i�ށB�Z�̐ď��ƌ���Ȃ��Ă��Z�̂��͂��܂����̂͂���1���B�x�B�����C�n�Ǝ��̈�A�̎��悪�I���ƊԔ�����ꂸ�u���X�o���h�̍Z�̏��t���А��悭�n�܂�̂��B���̋C�����͎����悭�킩��B����C2005�N�x�̏I�Ǝ���`���Ă݂���C�搶�́u�Z�̐ď��v�Ƃ������߂̌�Ƀu���X�i���y��������Ă����̂Ō����ɂ̓I�[�P�X�g���H�j�̉��t���n�܂�Z�̐ď��ւƈڂ��Ă������BOB�Ƃ��Ă͉��ƂȂ����߂����������Ă��܂����B |
|
�@ �@ |